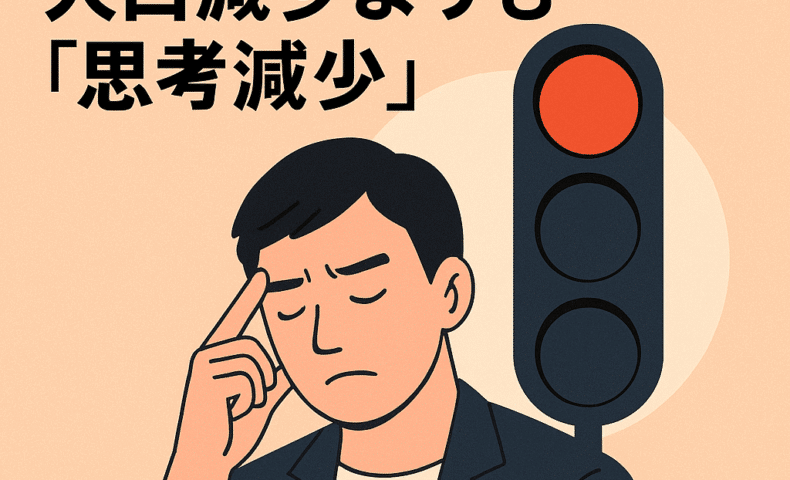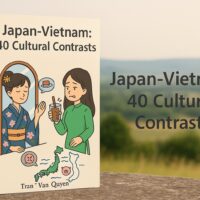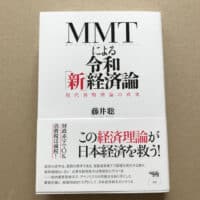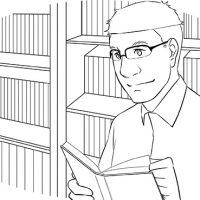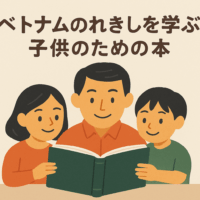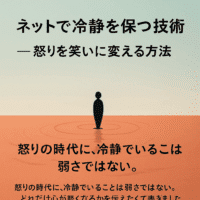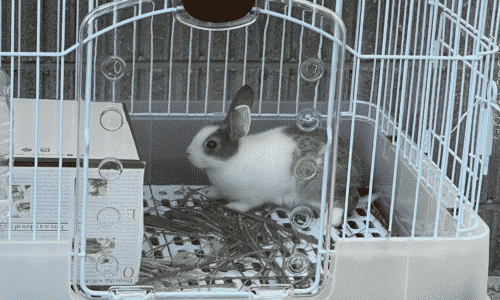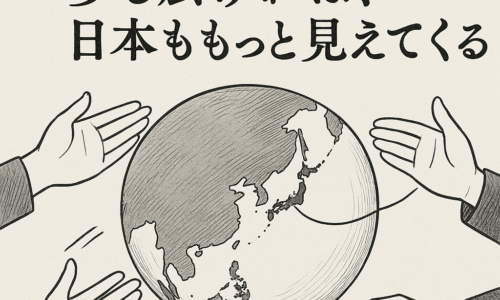Contents
📝このシリーズでは、Xに載せた「日本がなぜ停滞したのか」を
12の視点から少し細かく分析します。
第1回は――人口ではなく、「思考」が減っている話です。
⸻
■ 始めに:少子化よりも深刻な“別の減少”
日本では「人口減少」が国の最大の課題として語られている。
政治家もメディアも、少子化対策を繰り返し叫ぶ。
しかし――私がもっと深刻だと思うのは、「思考減少」だ。
人の数が減ったことより、考える人が減ったことの方が、社会を鈍らせている。
変化を恐れ、「今のままでいい」と思う空気が、ゆっくりと国全体を止めているように感じる。
⸻
■ 現象:考えない方が“楽”な社会
多くの人が「波風を立てない」ことを美徳としてきた。
会議では沈黙が安全、職場では同調が評価される。
問題を見ても、「自分には関係ない」と視線を逸らす。
結果として、考えない方が楽、意見しない方が安全という構造ができあがった。
これは単なる怠慢ではなく、長年の教育と組織文化の産物でもある。
⸻
■ 背景:学校と会社が“思考停止”を育てた
学校では「正解を早く答える人」が優秀とされ、
会社では「上の言うことを守る人」が優秀とされる。
こうして「考えるよりも、指示に従う方が得」と学んだ人々が、
社会の中心に立ち、次の世代にも同じ空気を伝えている。
少子化よりも怖いのは、“思考停止が文化になった国”である。
⸻
■ 比較:ベトナムとの違い
たとえばベトナムでは、社会全体がまだ“動いている”感覚がある。
議論は激しいし、若者は「自分の考え」を持っている。
もちろん混乱もあるが、混乱とは動いている証拠だ。
日本は整っている代わりに、動かない。
ベトナムはまだ整っていないが、動こうとしている。
どちらに未来があるかは、もう明らかだ。
⸻
■ 結論:考える人が増えれば、未来も増える
人口減少は避けられない。
しかし、思考減少は止められる。
一人ひとりが「考えること」を取り戻せば、
社会の“体温”はまた上がっていく。
国を支えるのは数ではなく、考える力なのだから。
⸻
📘次回:「失敗を恐れる文化」
――なぜ日本では、挑戦より“無難”が評価されるのか?