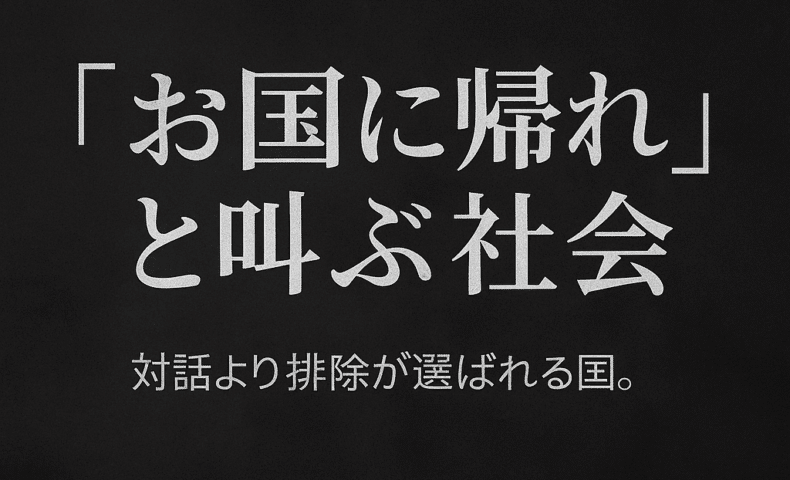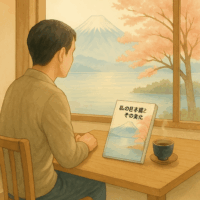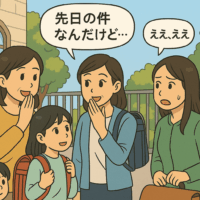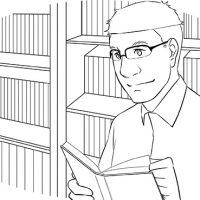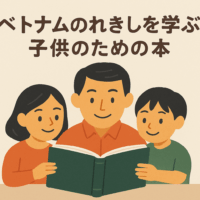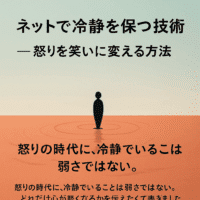Contents
言葉が軽くなり、怒りが日常になった時代
SNSを開けば、どこかで誰かが誰かに怒っている。
政治、経済、教育──そして「外国人」。
特にX(旧Twitter)では、
外国人が社会や政治について少しでも意見を述べると、
必ずのように現れる言葉がある。
「お国に帰れ」。
その一言は短く、単純で、そして強い。
だが、その強さの裏にあるのは論理ではなく、恐れだ。
異なる視点に出会った時、考える代わりに黙らせようとする反射。
それが、いまの日本の“言論空間”の現実を物語っている。
1.「お国に帰れ」という言葉に込められたもの
この言葉は、単なる排外主義の表現ではない。
それは、議論に負けた者の最終手段である。
反論できない人ほど、論点を相手の存在そのものにすり替える。
「あなたの意見は間違っている」ではなく、
「あなたはこの国の人間ではない」。
こうして、対話は終わり、沈黙だけが残る。
2.なぜ「議論」ではなく「排除」になるのか
日本社会の一部では、いまだに「対話よりも序列」が重んじられる。
年齢、立場、そして“内か外か”。
このヒエラルキーの中では、
異質な意見は“議論の対象”ではなく、“秩序の脅威”とみなされる。
だからこそ、理屈で向き合う代わりに、
「外の人」として排除する方が楽なのだ。
「お国に帰れ」という言葉は、
実は“日本を守る”ためではなく、
自分の安心領域を守るための呪文である。
3.SNSが作り出す「排除の快感」
SNSは、怒りと対立を拡散させる装置だ。
理性的な議論よりも、感情的な反応が優先される。
その結果、「お国に帰れ」は
一種の“拍手をもらえるセリフ”になった。
内容が空でも、
それを言えば“仲間”から「いいね」が返ってくる。
アルゴリズムが与えるのは「思考」ではなく、「承認」。
こうして、“無知が称賛され、理性が嘲笑される”空間ができあがる。
4.失われた「叱る大人」と、成熟しない言論文化
もう一つの問題は、「叱る大人」がいなくなったことだ。
かつては、他人を差別する発言をすれば、
周囲の大人が注意し、恥を教えた。
しかし今では、
大人自身がネットで幼稚な罵倒を繰り返している。
彼らは子どもに“常識”を教えるどころか、
“憎悪の使い方”を教えてしまっている。
教育の問題ではない。
承認欲求の暴走が世代を超えて伝染しているのだ。
5.「帰れ」と叫ぶ前に、向き合うべきもの
「お国に帰れ」と言う人々は、
実は“国を守る”のではなく、
“自分の不安”を守っている。
異なる意見を聞く勇気がなく、
自分が間違っている可能性を認めたくない。
だから相手を追い出す。
それが、最も簡単な「勝利」の形だからだ。
しかし、その勝利は虚しい。
なぜなら、相手を黙らせても現実は変わらないから。
議論を止めれば、社会は止まる。
そして止まった社会では、
「理性」よりも「声の大きさ」が力を持つようになる。
6.結論:帰るべきなのは“理性”の方だ
「お国に帰れ」と叫ぶ人たちへ。
外国人を帰らせる前に、
まず“理性”と“思考”をこの国に呼び戻してほしい。
対話のない社会は、
やがて自国の問題すら語れなくなる。
他人を追い出すことで安心を得る国は、
いつか自分自身をも追い出すことになるのだ。😶