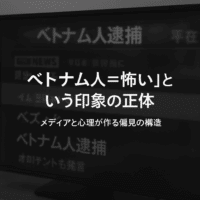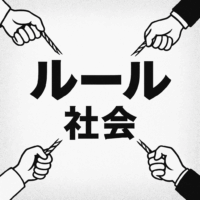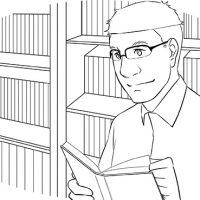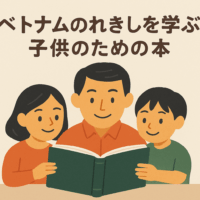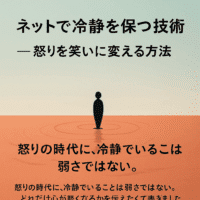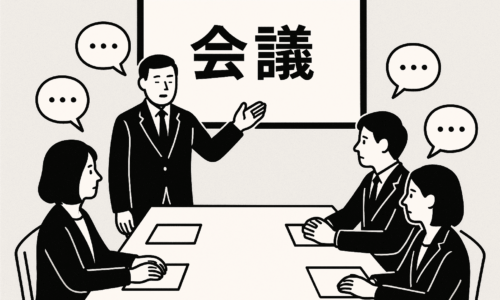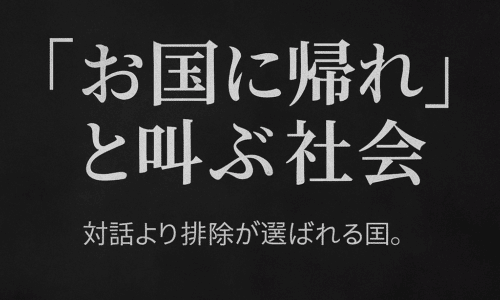教育を変えれば、人々の考え方が変わる。
人々の考え方が変われば、社会が変わる。
この二つの言葉は、ただの理想ではありません。
教育は、人間の価値観や行動の基礎をつくる「出発点」であり、そのあり方が社会の方向を決めます。
だからこそ、日本社会をより良くしたいなら、まず見直すべきは「教育の形」ではないでしょうか。
🎓 いまの教育に足りない視点
日本の教育は、長い間「平等」と「管理」を重視してきました。
確かに、それによって全国どこでも一定の学びを受けられる環境が整いました。
しかし、その裏で失われてきたのが「自由」と「柔軟さ」です。
たとえば、授業の進め方から保護者対応まで、ほとんどの学校が同じマニュアルに従っています。
それによりトラブルは減るかもしれませんが、現場の創造性や対応力は育ちにくい。
結果として、「考える力」よりも「従う力」が求められる教育になってしまっているのです。
🧭 「空気を読む」文化の限界
日本の学校では、集団の中で「協調性」や「空気を読む力」を身につけることが重視されます。
しかし、それが強くなりすぎると、「意見を言わないほうが安全」という空気が広がってしまいます。
社会に出たときにも、「違う意見を出す=波風を立てる」と感じてしまう。
それは個性を潰すだけでなく、企業や社会全体の成長を妨げることにもつながります。
今こそ、「空気を読む」よりも「意見を交わす」教育が求められています。
👨🏫 学校と先生に求められる変化
多くの先生は真面目で責任感が強い。
しかし、責任が重すぎるあまり、「決められたこと以外はしないほうが安全」という心理が働いています。
でも、ほんの少し変えるだけで、現場の空気は驚くほど変わります。
たとえば:
- 懇談をオンラインでも選べるようにする
- 紙の形式を減らしてデジタル化する
- 連絡は電話よりもメッセージ中心にする
- 宿題もコピーばかりではなく、時には先生のオリジナルを出すと生徒も喜ぶでしょう。
つまり、学校も先生も「安全な範囲内」で改善できる余地はたくさんあるのです。
少し変えるだけで、先生の負担は減り、子どもと向き合う時間が増える。
それは教育の本来の姿を取り戻すことにもつながります。
👪 保護者の側も変われる
教育は、学校だけに任せるものではありません。
家庭が子どもの学びに関心を持ち、先生と協力するだけで、学校の空気はずっと前向きになります。
問題が起きたときに「先生のせい」と突き放すのではなく、
「一緒に解決していきましょう」と言えるだけで、関係はまったく変わります。
先生を敵にせず、味方にする。
その一言が、子どもの安心と成長を支えるのです。
🌱 教育が変われば、社会が変わる
教育は、社会の鏡であり、未来の設計図でもあります。
学校が少し工夫し、先生が少し柔軟になり、保護者が少し歩み寄る──
その「少し」の積み重ねが、社会全体の変化を生むのです。
全部を変える必要はありません。
少し変えるだけで、人の意識は変わり、社会の空気も変わります。
今日できる“小さな一歩”こそが、明日の日本を明るくします。
📘 本記事は、著書『少しだけ変えれば、良くなる日本――外国人の視点から』の第1章「教育」をもとに再構成した内容です。
👉 Amazonで読む