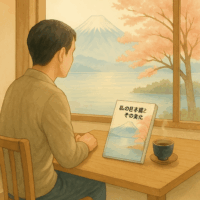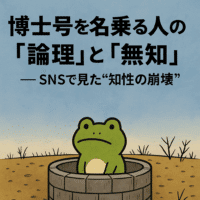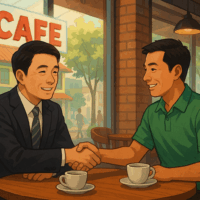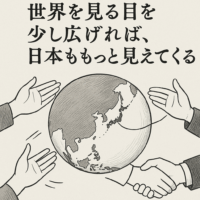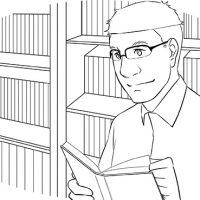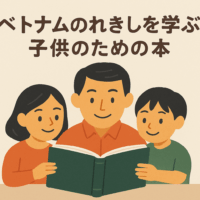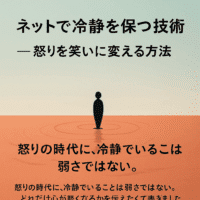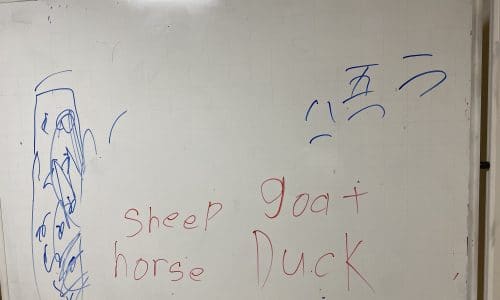Contents
――若者の能力より、年齢の順番が優先される社会
📝このシリーズでは、Xに載せた
「日本がなぜ停滞したのか」 をもとに、
12の視点から少し細かく分析しています。
第2回では「失敗を恐れる文化」を取り上げました。
今回の第3回は――「年功序列」という名の“足かせ”について考えます。
⸻
■ 導入:会社が「学校の延長」になった
日本では、学校を卒業すると多くの人が会社に就職する。
だが、よく見ればその会社は“学校の延長”のように見える。
先輩・後輩、出席・報告、上下関係。
そこにあるのは「成績」ではなく、「年次」で決まる序列。
まるで、教室がそのままオフィスに移動したかのようだ。
そして社会人になっても、「何年目だからこの役職」「年上だから偉い」――
そんな“順番文化”が当たり前に続いている。
⸻
■ 現象:能力よりも「順番」が優先される
多くの企業で評価されるのは成果ではなく“年数”だ。
どんなに優秀でも若ければ「まだ早い」と言われ、
どんなに無能でも年上なら「経験がある」として扱われる。
本来、年齢は「経験の長さ」を示すだけのはずが、
いつのまにか「価値そのもの」になってしまった。
結果として、若者は力を発揮する前に疲れ、
年配者は「降りられないポジション」に閉じ込められる。
――誰も得をしない構造が出来上がっている。
⸻
■ 背景:戦後日本が作った“安全な階段”
この仕組みは偶然ではない。
戦後の日本は「安定」を最優先に社会を再構築した。
終身雇用と年功序列は、社員を守るための“安全な階段”だった。
若いうちは給料が低くても、年を重ねれば上がる。
会社に忠誠を尽くせば、定年まで守られる。
――そんな“暗黙の契約”が何十年も続いてきた。
だが今、経済も人口も変わった。
それでも仕組みだけが残り、
階段は“安定”から“足かせ”へと変わってしまった。
⸻
■ 比較:ベトナムでは「実力が先」
ベトナムでは、年齢よりも“できるかどうか”が重視される。
若くても能力があればマネージャーになれるし、
上司より意見を言うことも珍しくない。
もちろん混乱もある。
しかし、その混乱こそが“成長のエネルギー”でもある。
日本は秩序の中で止まり、
ベトナムは混乱の中で動いている。
静かな国と、うるさい国。
でも未来を生むのは、いつだって“うるさい方”なのだ。
⸻
■ 結論:順番より、実力を信じる社会へ
「年功序列」を完全に否定する必要はない。
人を育てる時間も、経験を尊重する文化も大切だ。
だが、順番が目的化した瞬間に、社会は老化する。
誰が何歳でも、
“できる人が動ける社会”に変えていかなければ、
若い才能も、年長の知恵も生きない。
年齢ではなく、実力と誠意で信頼を築く。
それが、次の日本を動かすエンジンになるだろう。
⸻
📘次回:「会議のための会議」
――なぜ日本では、会議が多いのか?会議の役割版か?