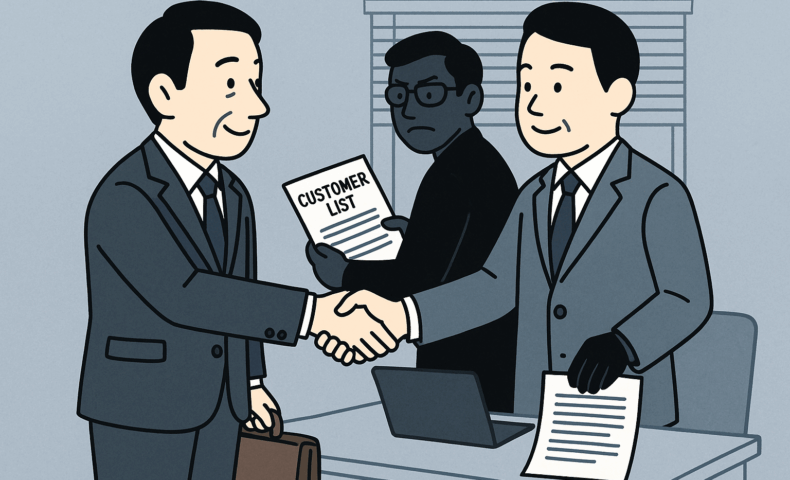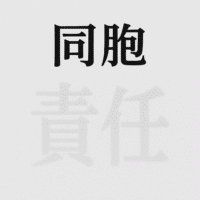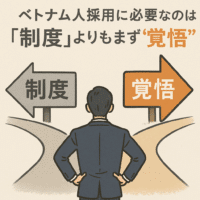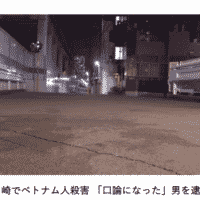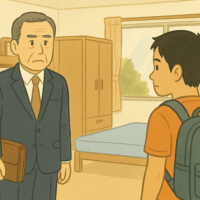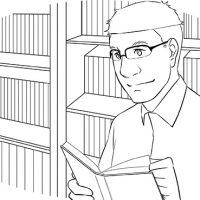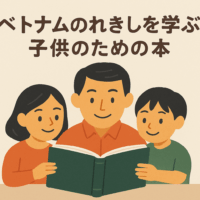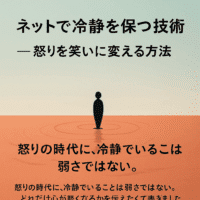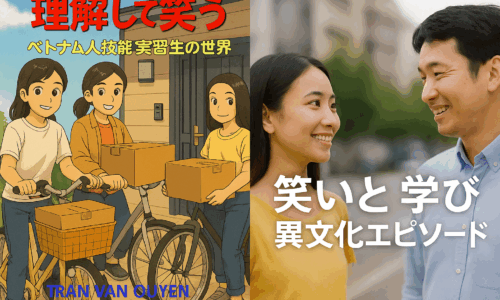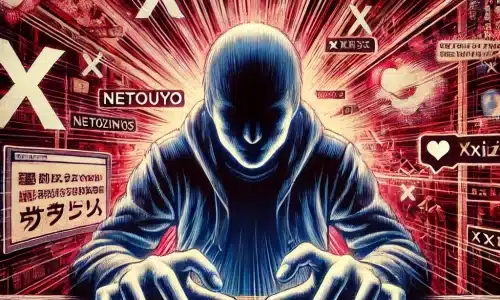Contents
──「信じすぎた通訳が、会社を壊した」
海外進出では、現地の言葉や文化を理解する「通訳」の存在が欠かせません。
しかし、その“信頼”が度を越えると、会社そのものを揺るがす結果を招くこともあります。
今回は、ベトナムで実際に起きた「通訳による会社乗っ取り事件」をご紹介します。
1/実際にあったケース(ストーリー)
ある日系企業は、ベトナム事業を本格化させるため、複数のベトナム人通訳を雇用しました。
その中に、特に気が利き、日本語も堪能で、何より「社長の言うことを素直に聞く」通訳が一人いました。
彼は常に笑顔で、社長の考えをよく理解し、逐語通訳というより「社長の分身」のように振る舞いました。
社長は次第に彼を信頼し、やがて日本では「お客様対応の代表通訳」、ベトナムでは「現地支社長」として抜擢。
人事・営業・契約・採用など、ほぼすべての権限を託しました。
──通訳から「実質経営者」への昇格です。
しかし、他の通訳や社員たちは、次第に違和感を抱き始めました。
- 支社長になった彼が、現地であからさまに威張るようになった
- 社長に伝える情報が“選別されている”ように感じる
- 一部の通訳が「危険だ」と感じて退職した
中には勇気を出して、「今のままでは会社が乗っ取られますよ」と忠告する者もいましたが、
社長は首を振りました。
「いや、彼は一番信頼できる。誰よりも私の考えを理解してくれている」
「文句を言う通訳たちは、きっと嫉妬しているだけだ」
──そうしている間に、事件は起きました。
その通訳は、社長の名前で契約や請求を操作できる立場を利用し、
日本の顧客と直接つながりを作り始めたのです。
顧客から見れば、「日本語が通じ、すぐ対応してくれる頼もしい現地責任者」。
彼はその信頼を利用し、少しずつ顧客を自分の別会社へと引き抜いていきました。
数か月後──日本本社には、注文も問い合わせも届かなくなりました。
顧客の大半は、すでに彼の会社に流れていたのです。
結果として、元の日系企業は経営が立ち行かなくなり倒産。
社長は多額の借金を抱え、夜逃げ同然に日本から姿を消しました。
2/背景にある「通訳への過信」と「ガバナンスの欠如」
この事件には、いくつかの盲点がありました。
① 通訳を“信頼しすぎる”構造
社長が現地語を話せず、現地事情も知らない場合、「信頼できる通訳」は命綱です。
しかし依存が過剰になると、通訳が「絶対的な存在」となり、他の声が届かなくなります。
② 経営と通訳の線引きが不明確
通訳は本来「言葉の橋渡し」ですが、気づけば人事・契約・採用なども決める立場に。
ガバナンス(内部統制)のルールを明確にせず、「便利だから任せた」ことが、リスクを生みました。
③ 顧客との直接接点を放置
現地責任者が顧客対応を行うのは自然ですが、
日本側が定期的な接触や信用確認を怠ると、顧客の信頼ごと現地に流れてしまいます。
3/教訓:通訳は“橋”であって“主役”ではない
信頼するのは大切です。
しかし、「過信」は危険。特に言葉と文化の壁がある場合、通訳は経営を左右するほどの力を持ちます。
- 通訳と経営の役割を明確に分ける
- 権限や署名ルールを文書化し、透明性を確保する
- 日本側と顧客が直接つながる仕組みを維持する
つまり、「通訳を信じる」前提であっても、裏切られない制度設計をしておくことが、経営者の責任なのです。
4/まとめ
「彼しかいない」──そう思える通訳に出会うことは幸運です。
しかし、ビジネスは信頼と制度の両輪で走るもの。
信頼だけに頼れば、いずれ転ぶ。
会社を守るためにも、通訳を“万能の神”にしてはいけません。
そして、「言葉が通じなくても、経営は通じる」──
その仕組みを持つことこそ、海外展開を成功させる第一歩なのです。
📘 本記事は、書籍
『ベトナムビジネスで失敗した日 本人たち: 文化の違いが招いた10の実話と教訓』
より抜粋・再編集した内容です。