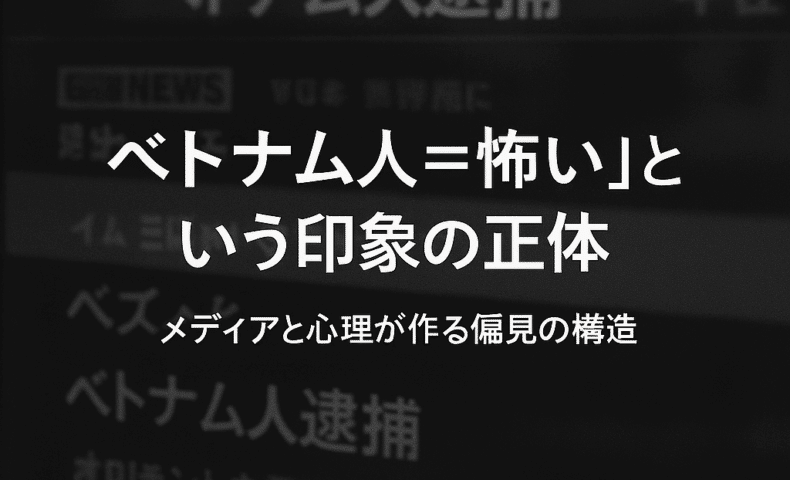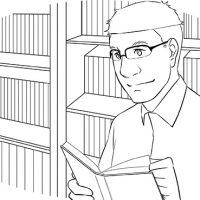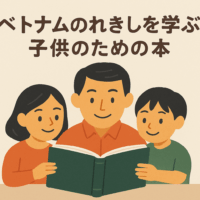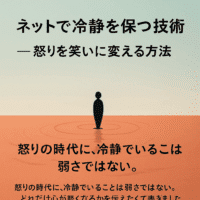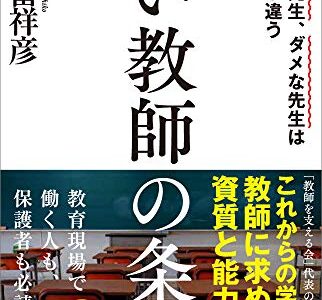Contents
別の記事(👉 ベトナム人は本当に“犯罪者”なのか?──報道と現実のあいだで)では、
ベトナム人による犯罪数と実際の“危険性”について、データに基づいて検証してきた。
では、それほどまでに「怖い」というイメージは、どのように生まれ、そして広がっていったのか。
この記事では、その“印象の形成”と“拡散のメカニズム”について、メディア・心理・社会の観点から探っていきたい。
1. メディアが作る「国籍イメージ」
まず注目すべきは、報道のあり方です。
日本人の容疑者が事件を起こした場合、ニュースでは「○○市の無職男性(45)」というように報じられます。
ところが、外国人が関与していると、「ベトナム人の○○容疑者」と国籍が強調されることが多いのです。
この「国籍の明示」がSNSで拡散されると、コメント欄には「やっぱりベトナム人は…」という固定観念が並び始めます。
同じ罪でも、誰が犯したかによって報道の扱いが変わる。
その違いが積み重なって、「外国人犯罪=危険」という構図が社会の中に刷り込まれていきます。
やがて一つの事件が、民族全体の性格や文化と結びつけられ、あたかも「国民性の問題」であるかのように語られてしまうのです。
2. 記憶に残るニュースの“心理的トリック”
心理学の視点から見ると、人間の脳は「印象的な出来事ほど強く記憶する」傾向があります。
そして、私たちは“自分とは違う存在”に対して、より強い印象を持ちやすい。
日本社会では、ベトナム語を話し、仲間同士で行動する技能実習生たちは、多くの人にとって“非日常的な存在”です。
そこに「ベトナム人が犯罪を犯した」という報道が重なると、脳の中では「異質」+「犯罪」=「怖い」という無意識の公式が出来上がります。
これが繰り返されることで、事実以上に「怖い」という印象が強化され、やがて“現実”のように信じ込まれてしまうのです。
つまり、「怖い」と感じる理由の多くは、実際の危険ではなく、脳がそう“錯覚してしまう”仕組みにあります。
3. 情報拡散のスピードと“恐怖の連鎖”
メディアの形も、この10年で大きく変わりました。
かつては新聞やテレビが主な情報源でしたが、今はSNS、ブログ、YouTube、まとめサイトなど、誰もが「発信者」になれる時代です。
ひとつの事件が何度も異なる媒体で報じられ、クリックされ、引用されることで、印象はどんどん増幅していきます。
そして、メディアは「真実」だけでなく「注目」も求めるようになりました。
クリック数や再生回数が利益につながる以上、「不安」や「恐怖」を煽る内容が優先される。
その結果、「ベトナム人による事件」という言葉が繰り返し目に入る構造が生まれ、人々の潜在意識に「ベトナム人=危険」というステレオタイプが定着してしまうのです。
4. 「怖い」という感情の正体
では、「怖い」とは一体どこから来る感情なのでしょうか。
金曜の夜、駅前で大声を上げる酔っぱらいのサラリーマン。
舌打ちをしながら自転車をこぐ若者。
河川敷でBBQをするベトナム人グループに怒鳴る高齢男性。
──こうした場面を見て「少し怖い」と感じたことがある人もいるでしょう。
しかし、これらの多くは“危険”だから怖いのではなく、“慣れていない”から怖いのです。
つまり、「怖さ」は実際の危険性ではなく、文化的な違いによる“戸惑い”や“予測不能さ”から生まれるもの。
そうした違いが積み重なると、偏見という形で社会に固定されていきます。
まとめ:印象と現実のあいだにある“壁”を見つめる
「ベトナム人は怖い」という言葉の裏には、実はデータではなく「印象」がある。
その印象は、報道の書き方・心理のクセ・情報拡散の仕組みが重なってできた“人工的な恐怖”にすぎません。
しかし、私たちがその構造を理解すれば、恐怖は溶けていきます。
理解の先には、共生への第一歩があるのです。
📘 もっと深く知りたい方へ:
『ベトナム人は“犯罪者”なのか?──その偏見と現実』
👉 Amazonで見る
メディアが作る「印象」と、現実とのギャップ。
その狭間に潜む偏見のメカニズムを、データと心理の両面から解き明かします。