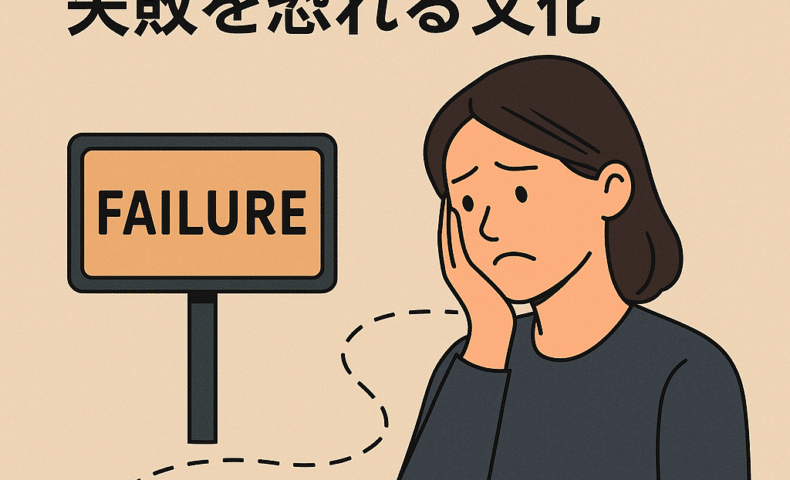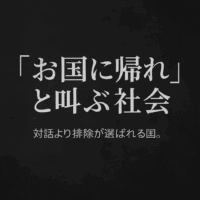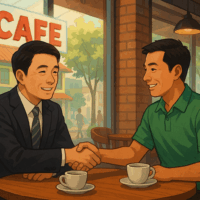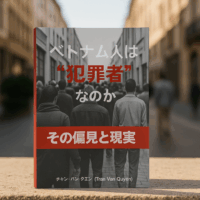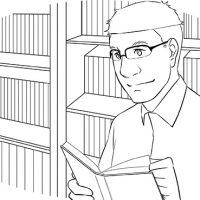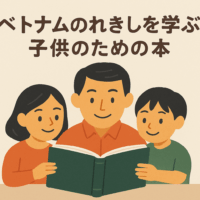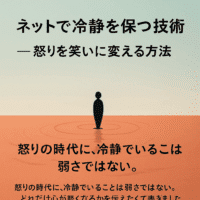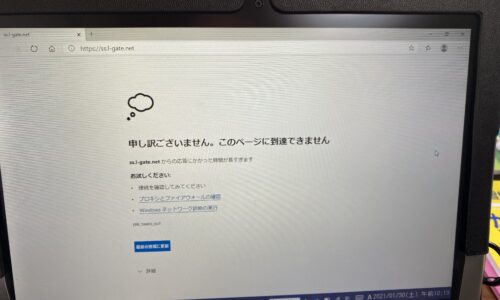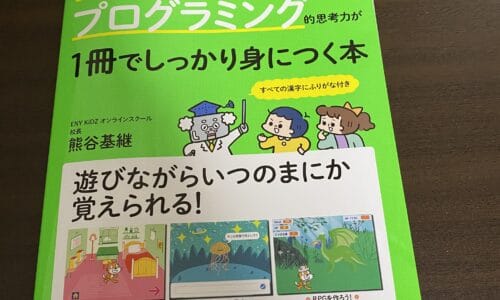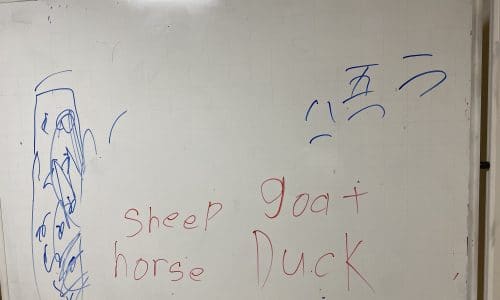――なぜ日本では、挑戦より“無難”が評価されるのか?
📝このシリーズでは、Xに載せた「日本がなぜ停滞したのか」を
12の視点から少し細かく分析します。
第1回は――人口ではなく、「思考」が減っている話です。
この第2回は失敗を恐れる文化の話です。
⸻
■ 導入:失敗=終わり、という空気
「失敗は成功のもと」と言う言葉はある。
しかし、日本でその言葉を本気で信じている人は、どれくらいいるだろうか。
多くの人にとって、失敗とは“やり直せないもの”、
つまり「人生の汚点」である。
そのため、新しいことに挑戦するよりも、
「失敗しないこと」自体が目的になってしまう。
⸻
■ 現象:挑戦よりも“無難”が評価される社会
学校でも会社でも、評価されるのは「失敗しない人」だ。
目立たず、間違えず、周りと同じように動く人。
そういう人が「安心できる人材」として重宝される。
一方で、新しい提案や異なる意見を出す人は、
「リスクを作る人」「空気を乱す人」と見なされやすい。
その結果、職場では誰も手を挙げず、
学校では誰も質問をしない。
こうして日本社会は、“安全運転”ばかりが上手くなった。
だが、安全運転では、新しい景色にはたどり着けない。
⸻
■ 背景:失敗を「恥」と結びつける文化
なぜ日本ではここまで失敗を恐れるのか。
その根には、「恥の文化」と呼ばれる価値観がある。
欧米では「失敗=学び」として共有されるが、
日本では「失敗=信用の喪失」になりやすい。
だから一度のミスが、個人の評価や人間関係を大きく揺るがす。
そして、周囲もまた「失敗した人を静かに遠ざける」。
結果として、挑戦しない方が安全という選択が合理的になってしまう。
⸻
■ 比較:ベトナムでは“転んでも立つ”
たとえばベトナムでは、失敗しても笑ってやり直す人が多い。
商売に失敗しても、次の日には別の商売を始めている。
周囲も「また頑張ればいい」と声をかける。
つまり、失敗が“終わり”ではなく“通過点”として受け入れられているのだ。
一方、日本では一度つまずくと、「あの人はダメだった」と記憶される。
失敗を「恥」として記録する社会に、
新しい挑戦が根づくことは難しい。
⸻
■ 結論:失敗を笑える社会に
「失敗を恐れない」とは、
「軽率に行動する」ことではない。
むしろ、「失敗を通して学ぶ」力を信じることだ。
もし社会全体が“失敗を笑える”ようになれば、
もっと多くの人が動き出すだろう。
停滞しているのは、経済ではなく――
失敗を許せない心なのかもしれない。
⸻
📘次回:「年功序列という名の“足かせ”」
――なぜ日本では、能力より“順番”が重視されるのか?